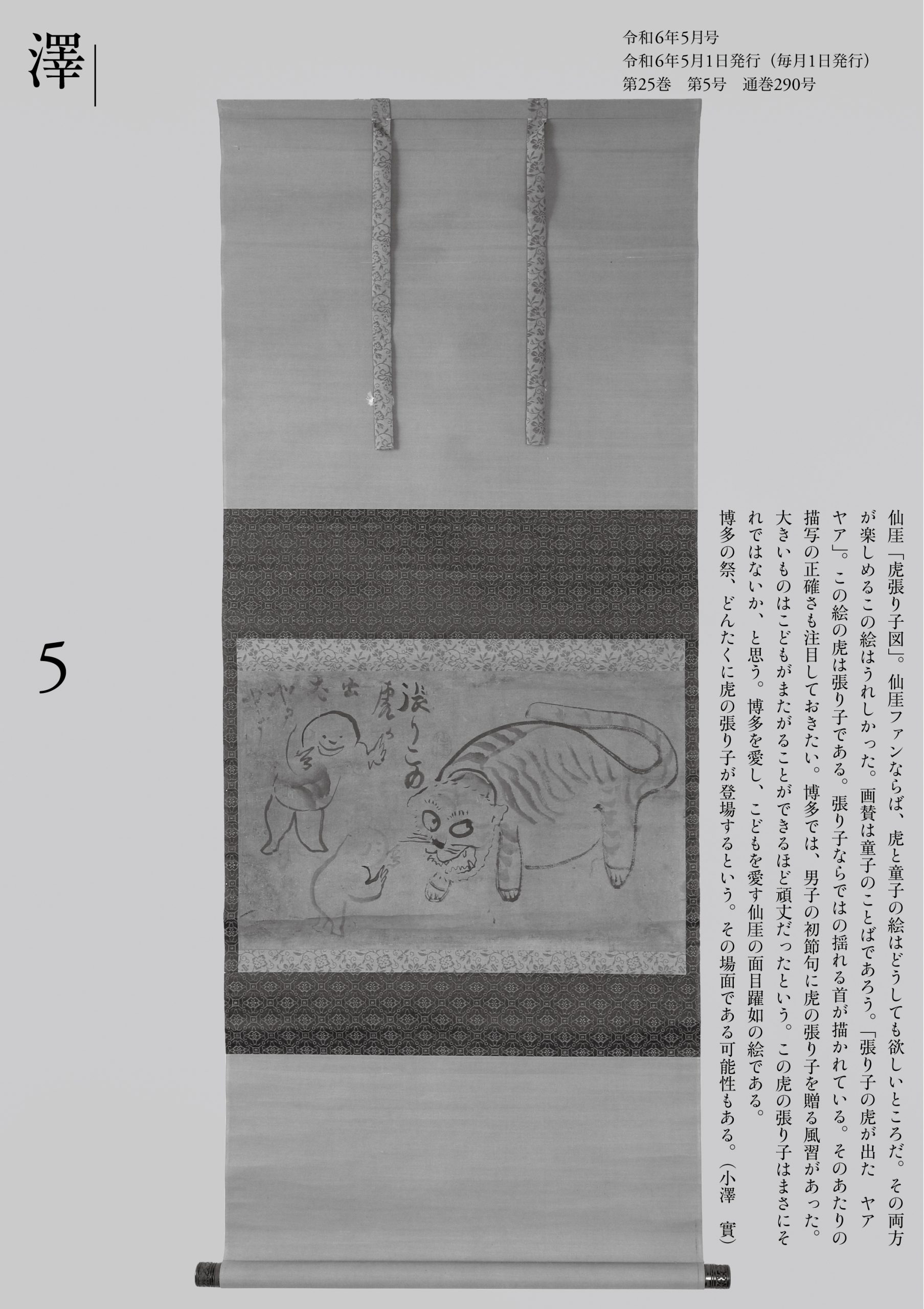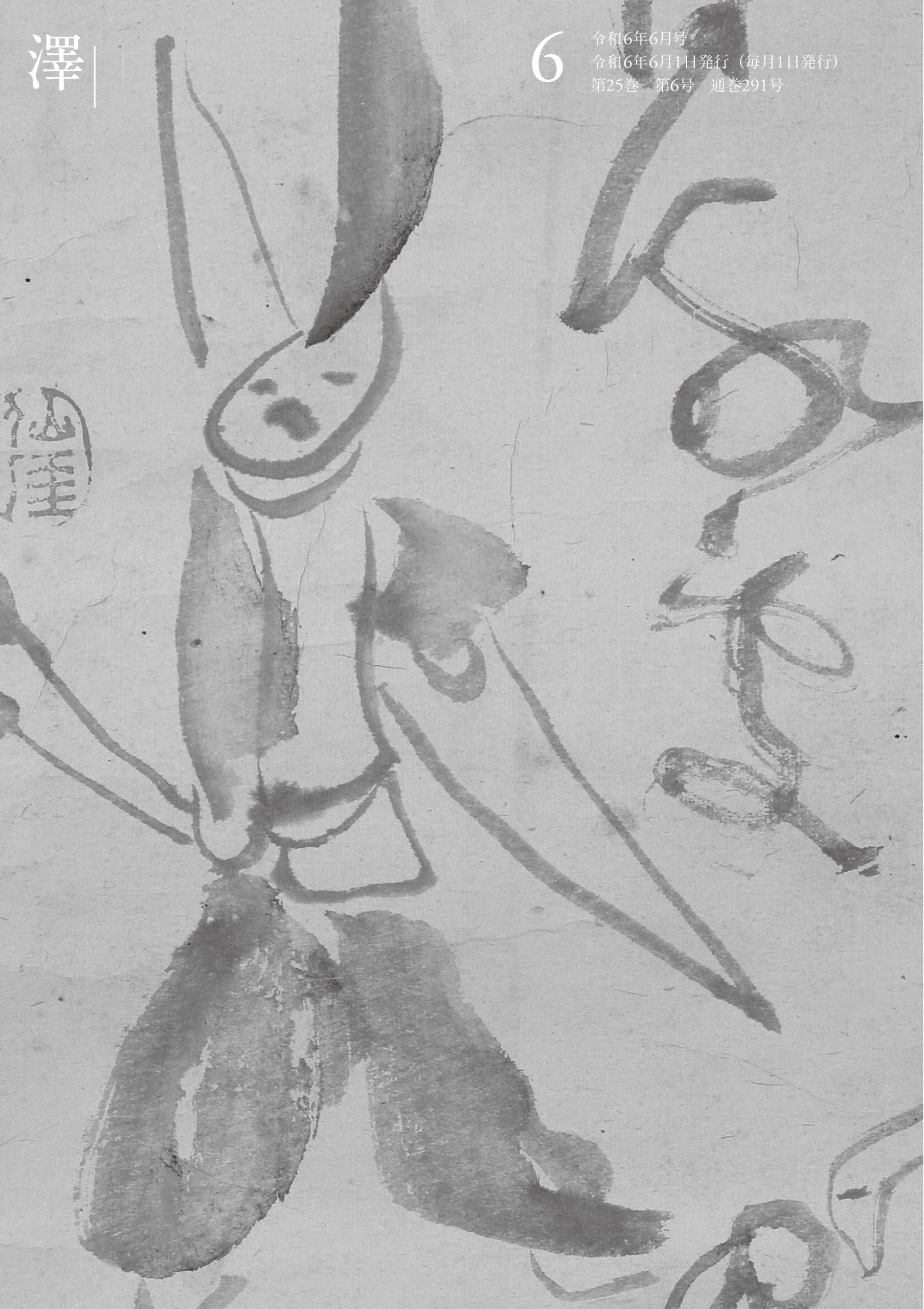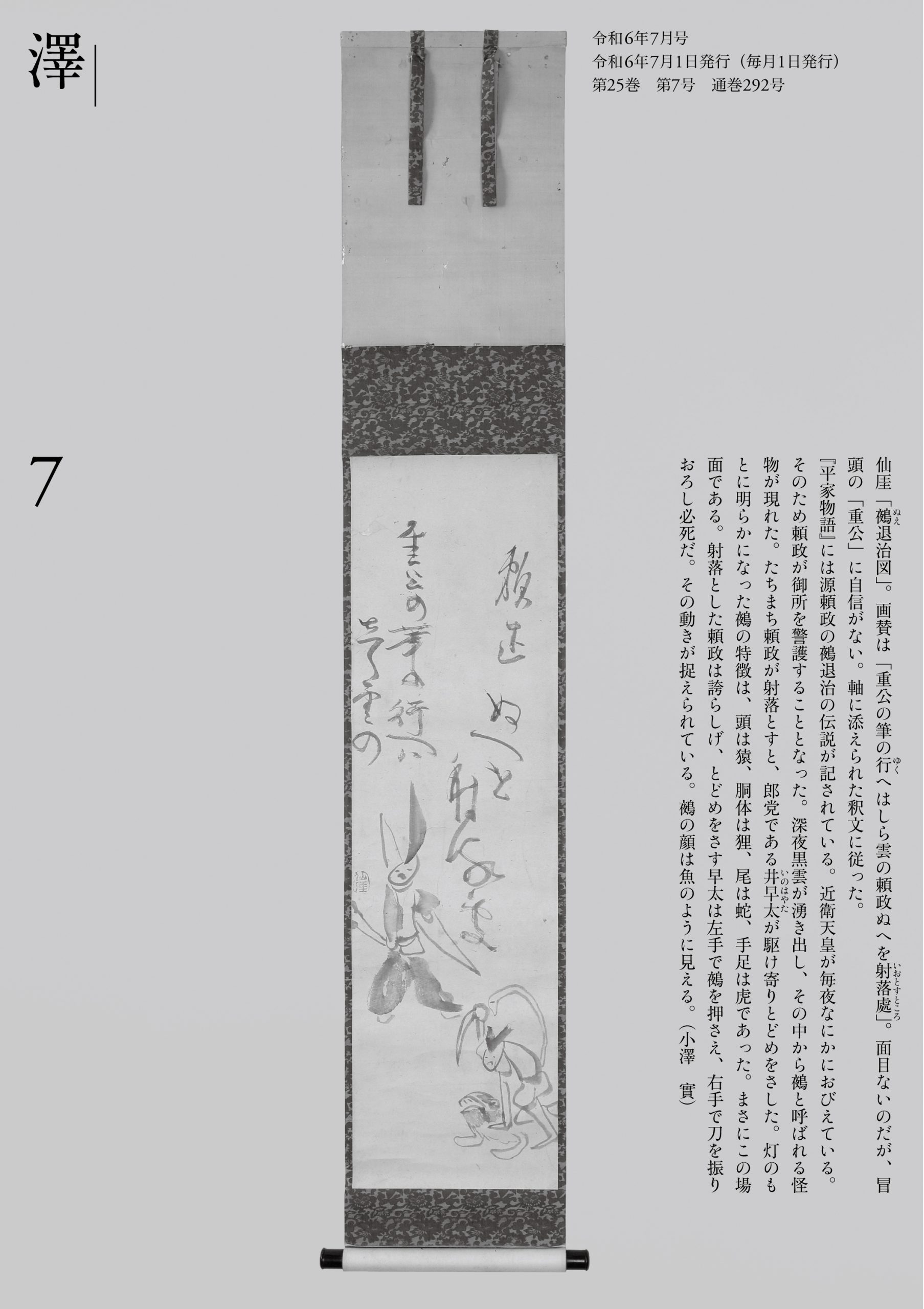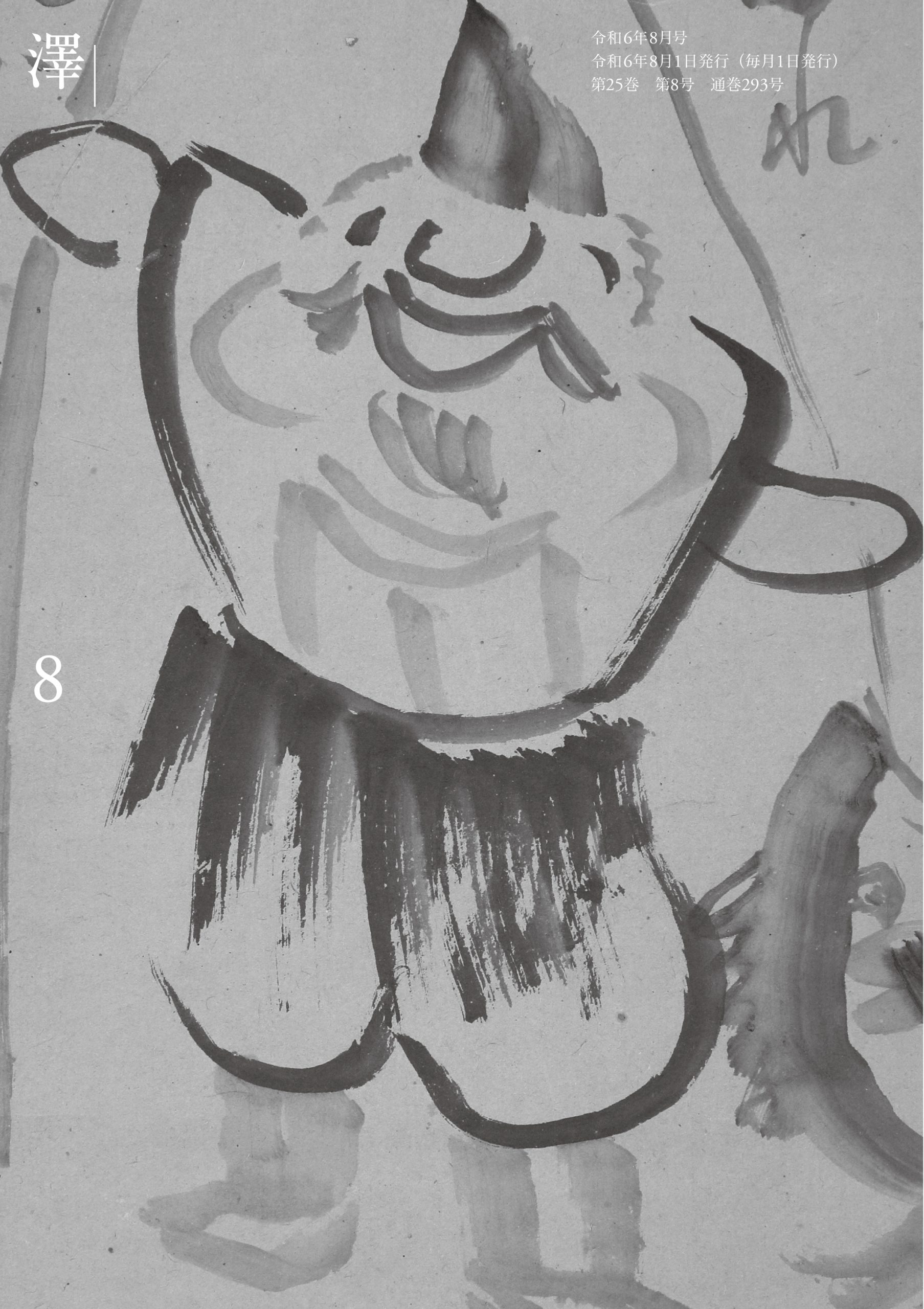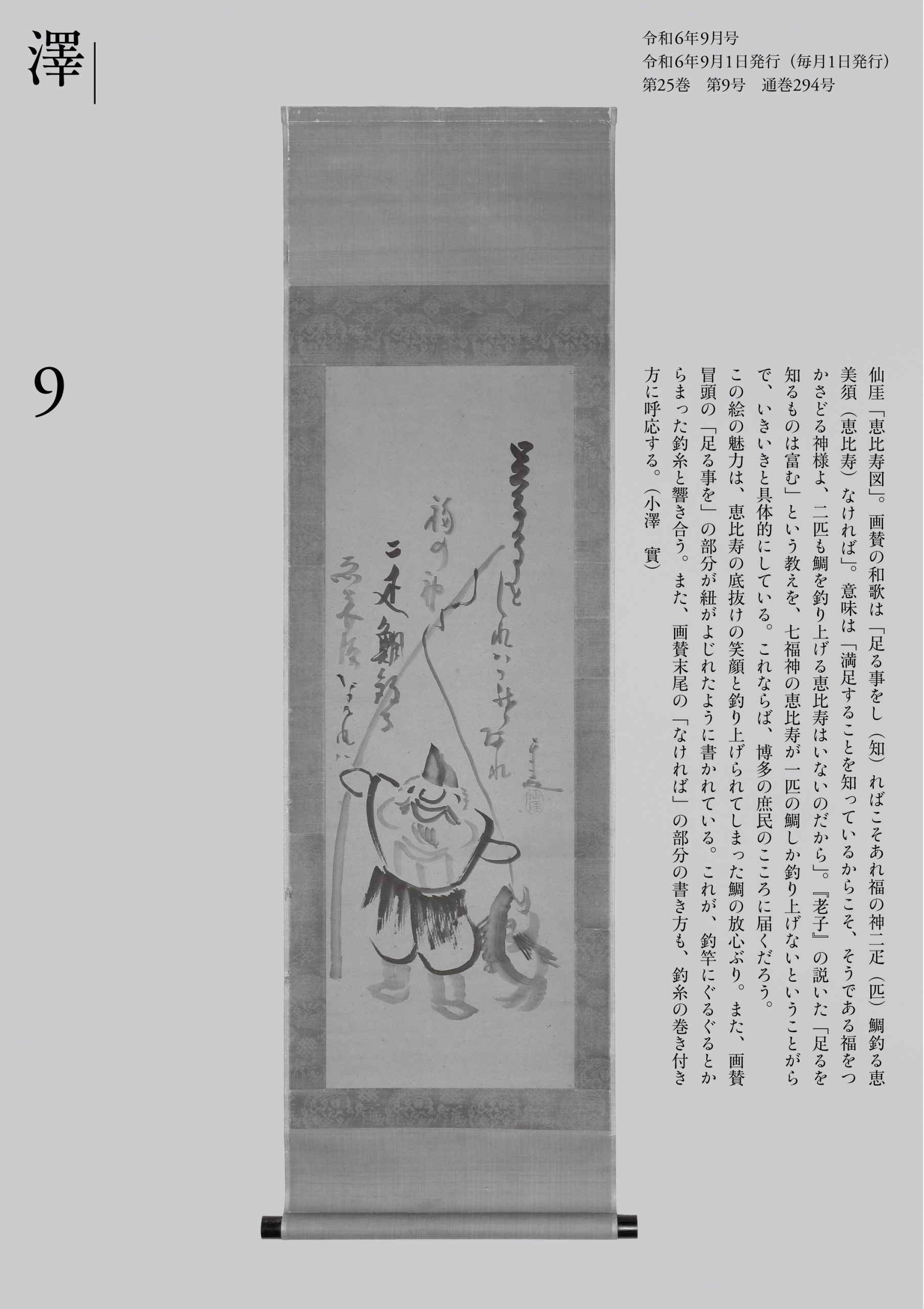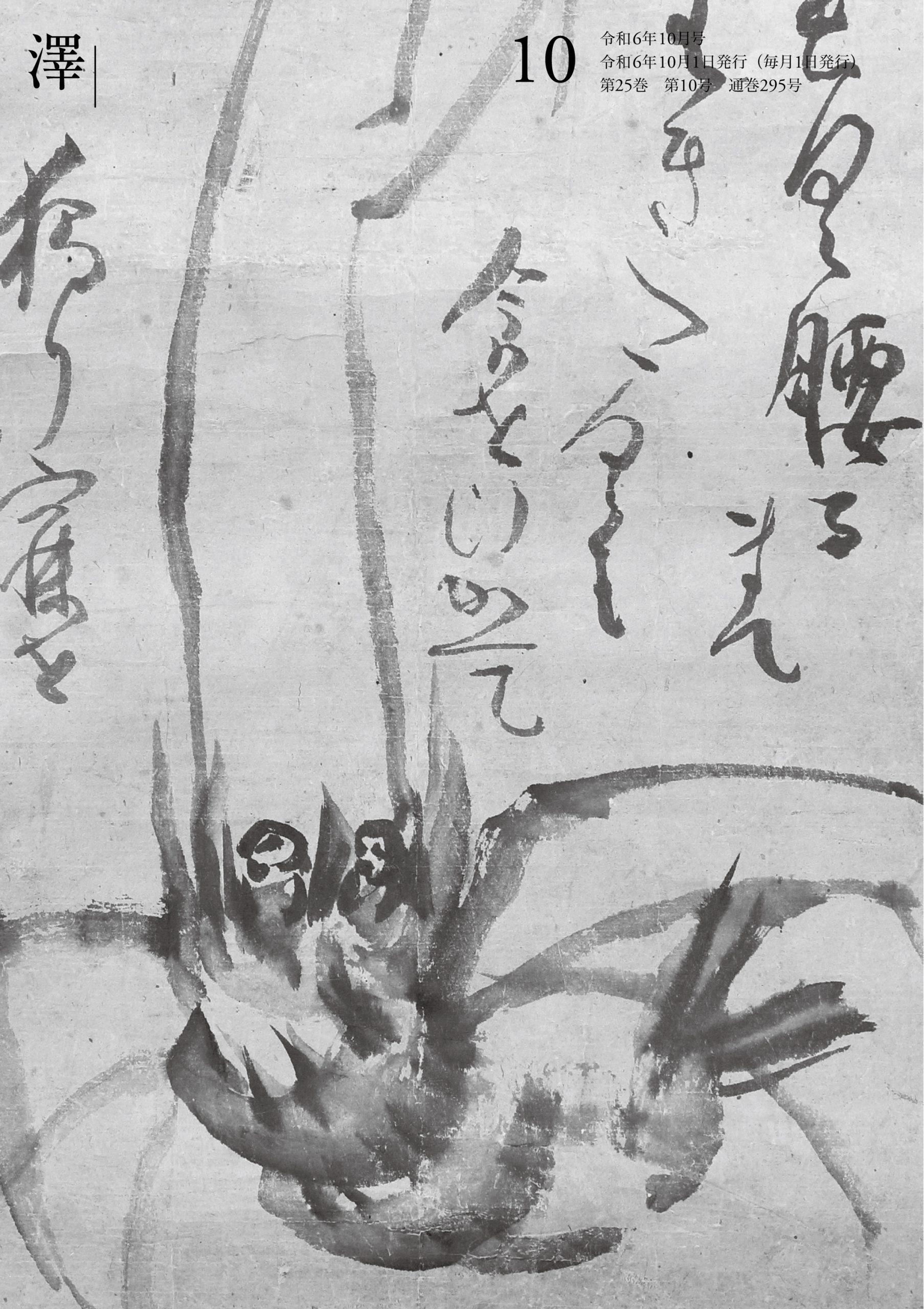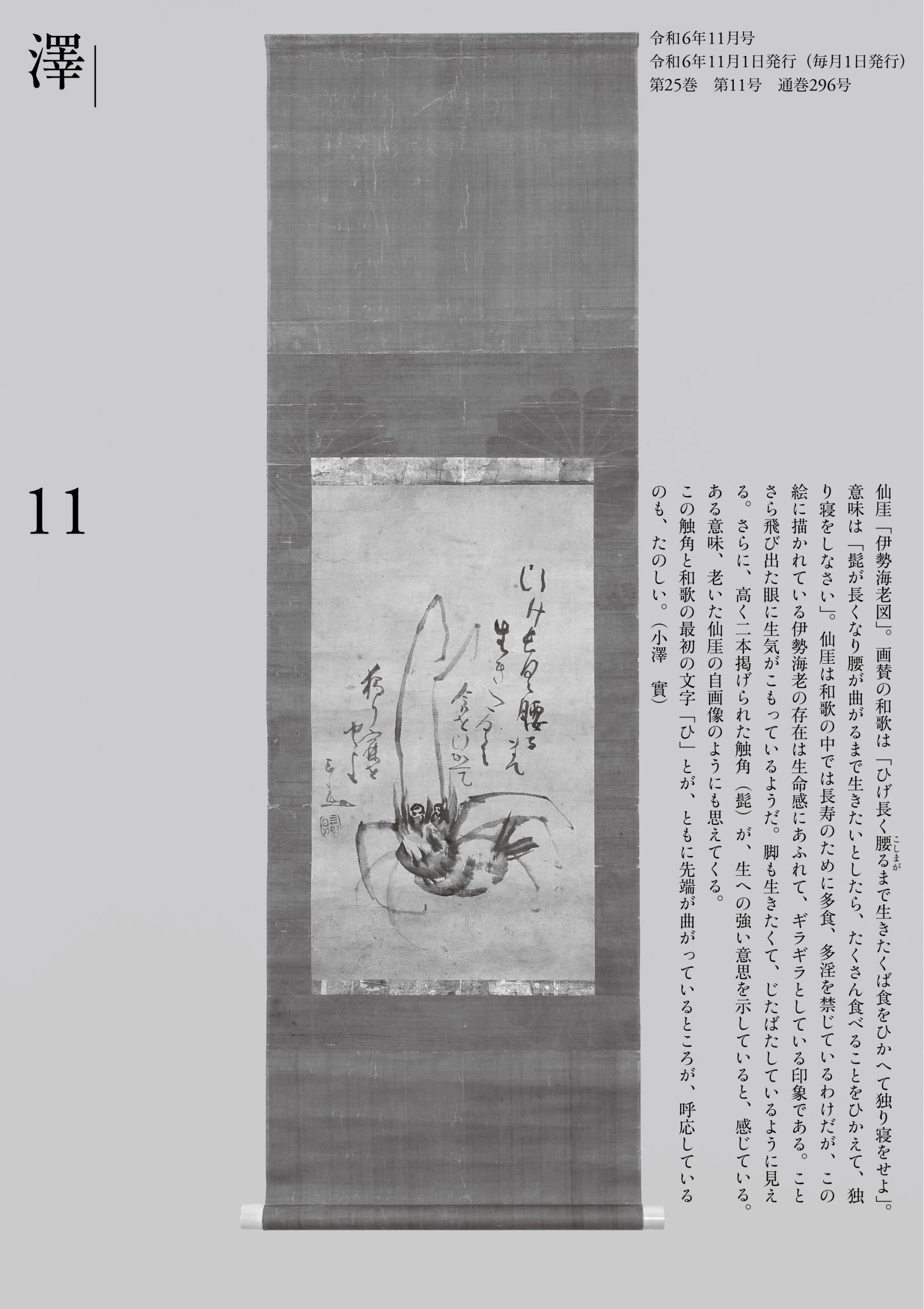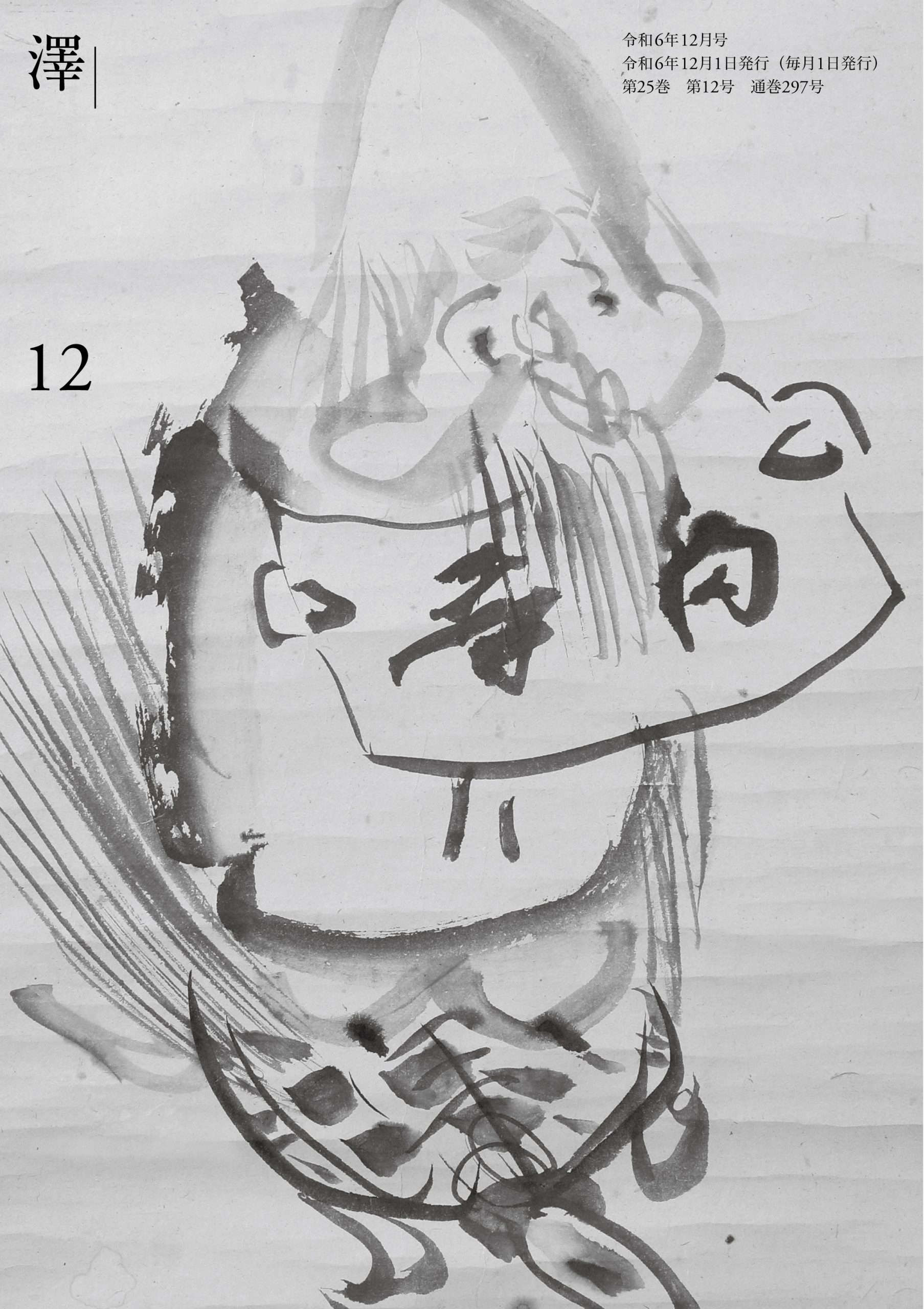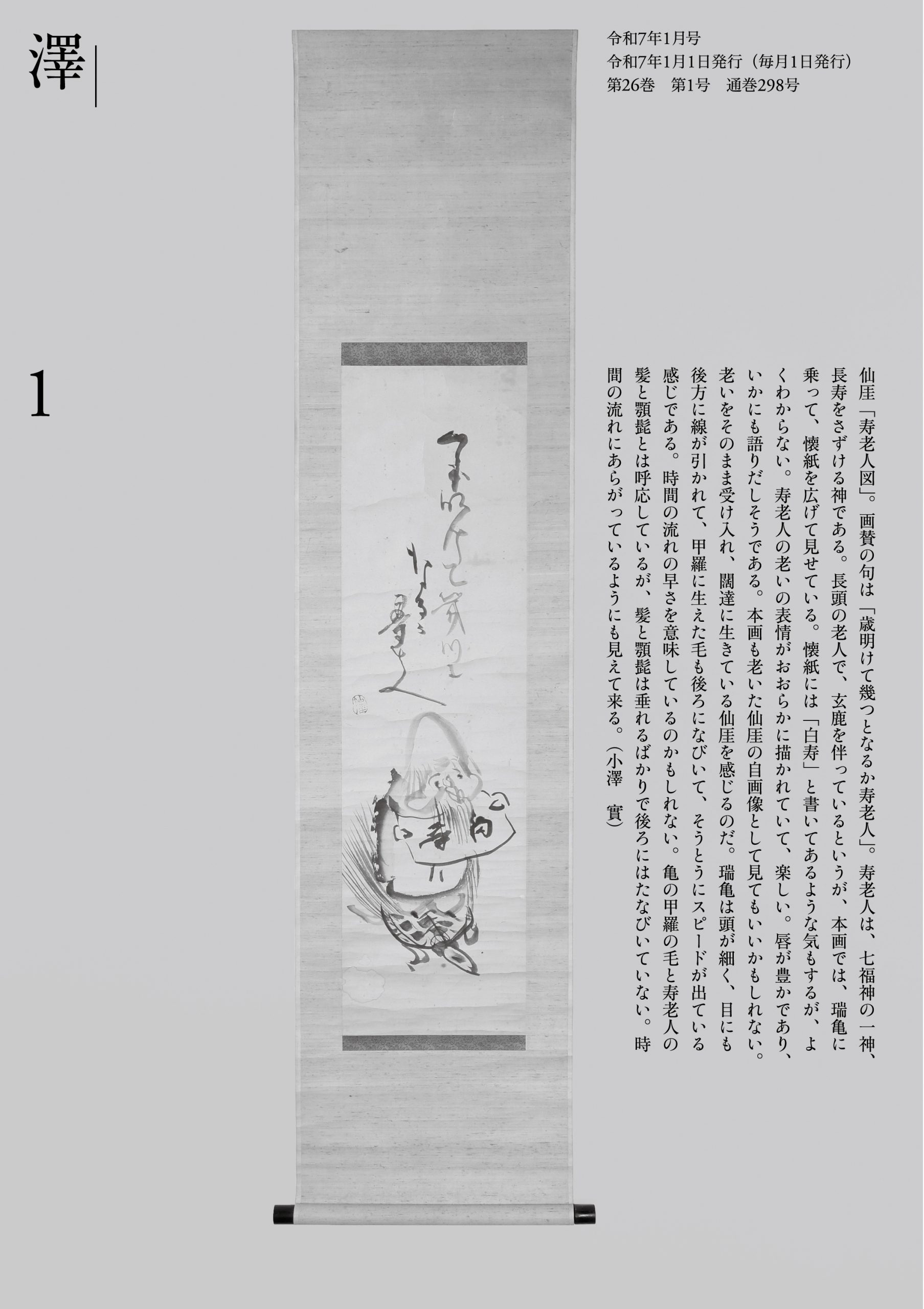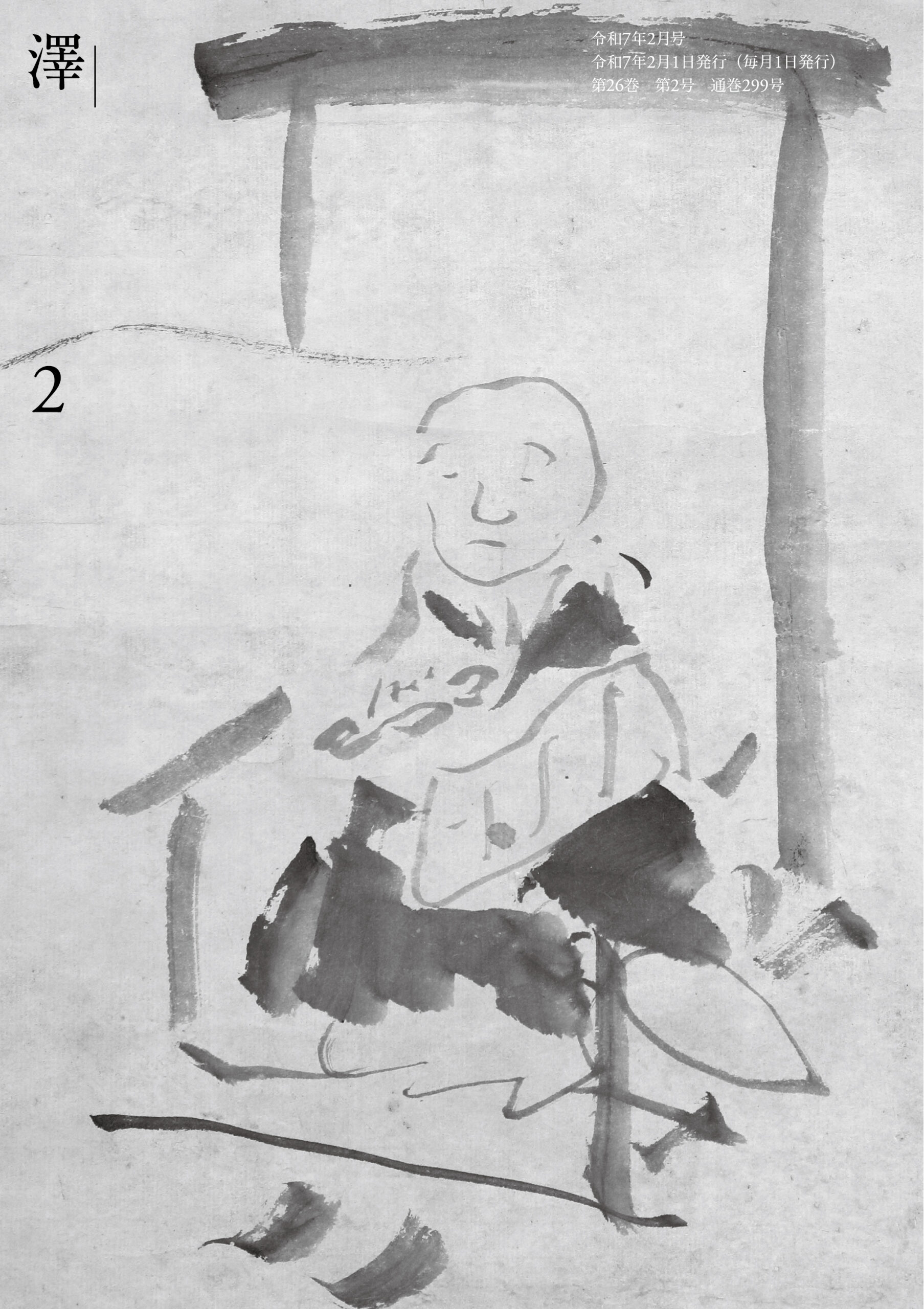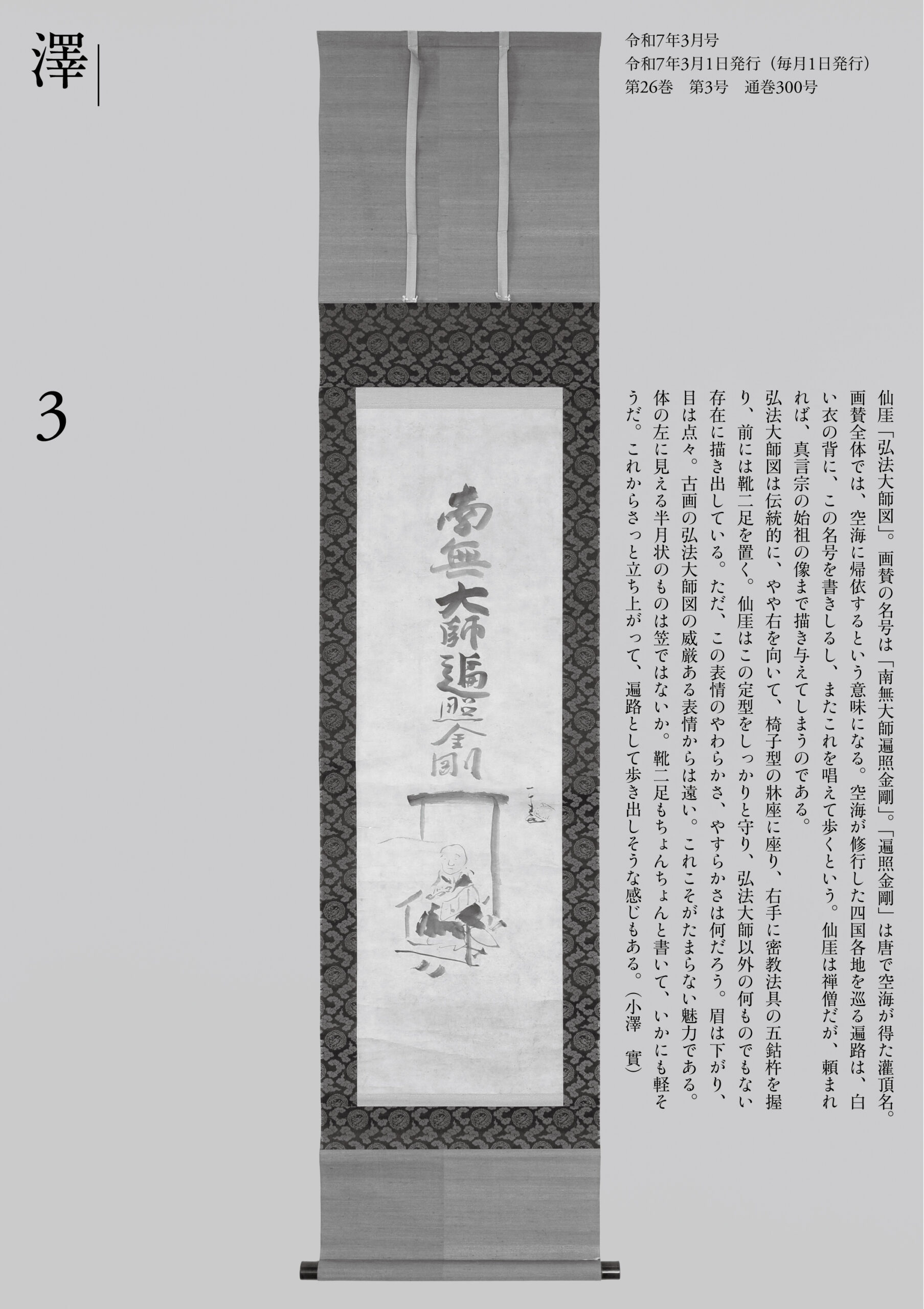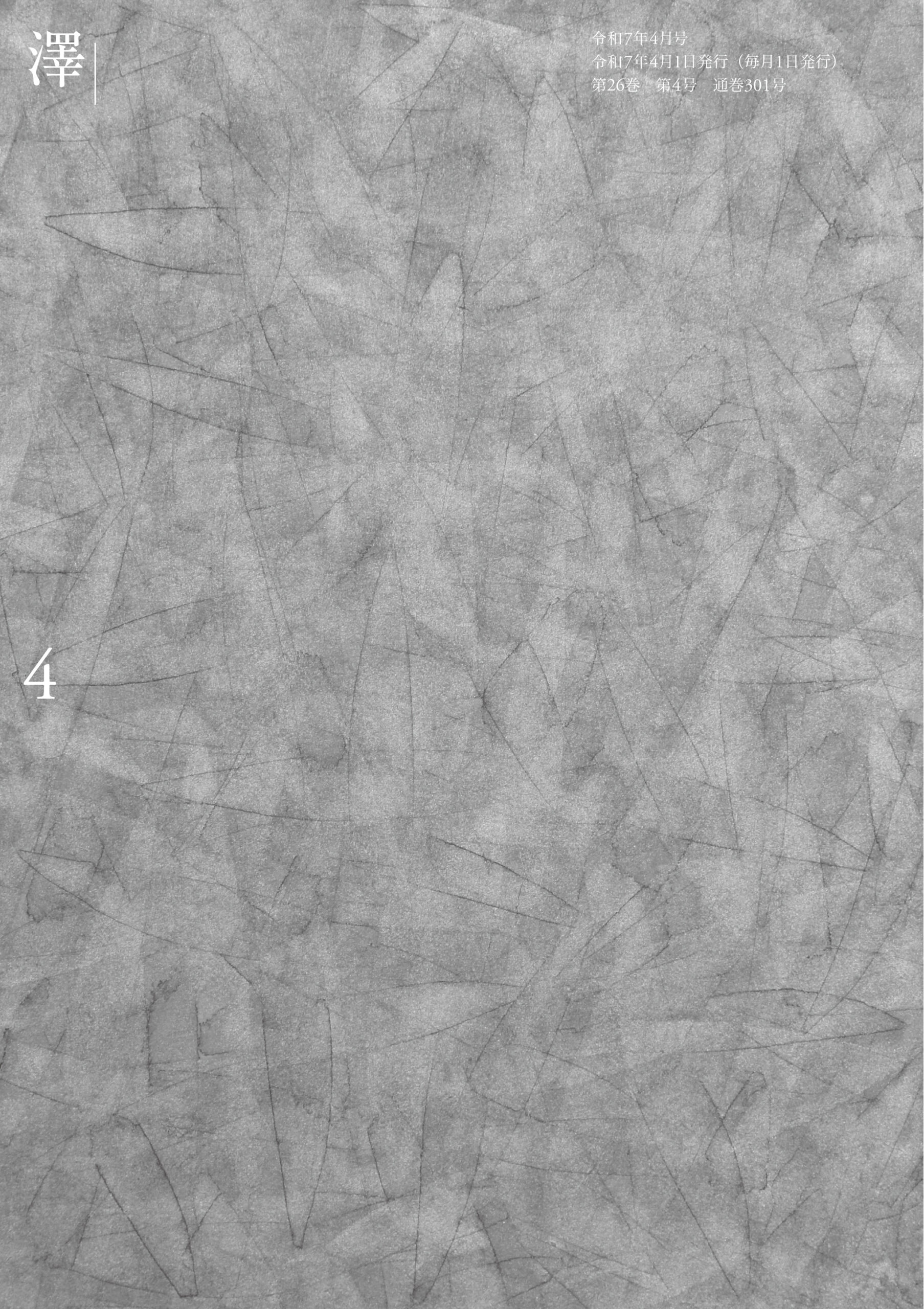6月号/小澤實十五句
-
ビ ー ル 飲 ま ず ば
沢筋の雪吹きだまりなほ消えず
山々簇生有明山となる春ぞ
残雪の有明山や墓照りぬ
畔北側の残雪しるしはるかまで
山ひとつ疎林や残雪をあるく
鳶の旋回はるかに鳶の旋回春
死後も父書き仕事せり春の雪
-
安曇野の畔のはだらに青むなり
春の田に轍の深くうねりたる
春の田の一隅にして葱つくる
はや駆けてサラブレッドの仔馬かな
母馬へ仔馬たちまち駆けもどる
草に脚のべて仔馬の休みたる
ビール飲まずば一日終はらずと君は
一冊の夏野なりけりみづみづし
6月号/澤四十句/小澤實選
-
- 落椿赤色赤光浄土なす
- 相澤亮平
- がざみの鋏に指はさませて捕る叔父よ
- 戸田いぬふぐり
- レターパック厚し「やしようま」並べ入れ
- 川崎榮子
- 春暁の夫よ便座を下げたまへ
- 小澤たえみ
- 春田打つ八ヶ岳南麓の火山灰壌土
- 鶴見澄子
- パーマ失敗の吾の頭巨大や卒業式
- 信太 蓬
- プライベートゾーン絵本に習ふ入園児
- 平嶋さやか
- 白蓮に師事し百歳八重桜
- 山田渥子
- 朝寝の父揺すり起こすや馬乗に
- 野口桐花
- ストーンヘンジ春塵に見ゆなほ遠し
- 野崎海芋
- 泥鰌掘る父のスコップ子のシャベル
- 中村敏彦
- 我が遺影撮りたしかかる花の日に
- 佐藤昭子
- プールには入つたものの泳げません
- 上村ヒナコ
- 涅槃図や目をおほひ猿泣くばかり
- 寺島 麦
- 名札返す帰寮の友や春の雪
- 山下希記
- つちふるや剝きし卵に小さき傷
- 酒井拓夢
- 天草や朝日映えたる桜鯛
- 松井宏文
- 忘れていい生きてゐてくれ卒業訓話
- 大堀 柔
- ローンまだ続く墓とふ彼岸道
- 竹村さぎり
- 粗大ごみ回収券貼られしギター春の闇
- 本村早紀
-
- 刈田道セーラー服を喪服とし
- 木内縉太
- 車椅子ランナーの前傾深し春疾風
- 近藤信男
- 春宵のマジシャンが出す白いピアノ
- 林 達男
- 花咲くや舞妓十人足拍子
- 檜田陽子
- 元彼を呪う人形花月夜
- えんどうようこ
- 血圧計ぎゆつ春セーターの腕
- 上林七菓
- 入学の孫ジュースの乾杯何度でも
- 柏野孝子
- 金借りて金返したり罌粟の花
- 沼田美山
- 火の上の栄螺回すや軍手して
- 中井亜由
- 遠隔操作に春田の雑草刈る老婆
- 篠田洋子
- 指に押し薄氷回す鉢の中
- 豊田・ヌー
- 寝る前の手足ぶらぶら体操春
- 天野正子
- 「鈍感なれ」が魔法の呪文豆の花
- 江藤鳥歩
- 胡麻に和へ菜の花備前片口に
- 青沼まみ
- 炭酸の飛び出る粒や春日影
- ほしかなた
- 乾燥機の円窓春帽子まはる
- 富田圭香
- 抱く猫にたくましき髭春夕べ
- 村戸俊子
- デュルンと消えしビデオ通話や朧の夜
- 瀨戸山海月
- 忘言の契りの友や啄木忌
- 木津川珠枝
- 猫と児に他界のひらく春の路地
- 酒井 徹
6月号/選後独言/小澤實・仏教用語を操る
-
- 落椿赤色赤光浄土なす
- 相澤亮平
落椿が、赤い色をして、赤い光を放っている、そこはこの世ならぬ浄土となっているのだ。
斎藤茂吉の第一歌集名が、『赤光』であった。その題は『仏説阿弥陀経』から取られているという。阿弥陀仏の浄土に咲く蓮の花の描写「青色青光 黄色黄光 赤色赤光 白色白光」からである。
掲出句はまさにその描写の「赤色赤光」を引用して、落椿の美しさを讃えていることになる。落椿の奥に浄土に咲く蓮というものの普遍的な美を感じ取っているのである。
「赤色赤光」という音からは、地に満ちている落椿の互いに触れ合っている質感までも感じ取ることもできる。仏教用語を自在に操って、ひとつの浄土を打ち立てているのだ。 -
- がざみの鋏に指はさませて捕る叔父よ
- 戸田いぬふぐり
がざみはワタリガニ科のかに。内湾に生息するという。
がざみの鋏に指をはさませて、捕らえる叔父よ。
「指はさませて」と書いているが、ある程度の大きさのあるがざみならば、この行為はそうとうな痛みを伴うと思う。自分の指を仮に餌として差し出し、挟んでくるがざみの身を捕らえているわけだ。この句の叔父は数限りなくこの経験を重ねているような気がする。
がざみは、昼は海底の砂の中に潜み、夜間に出て、活動するという。叔父は、夜の海に出かけているのか。「叔父よ」には、深い敬意が込められているのを感じる。 -
- レターパック厚し「やしようま」並べ入れ
- 川崎榮子
レターパックは、日本郵便会社のサービスで、小さな荷物を送ることができる商品。A4ファイルサイズのパックに荷物を入れて発送する。
やしょうまは涅槃会の供物。涅槃会は二月十五日、亡くなった釈迦を祀る行事である。その際、仏壇に供える米粉を練ったものに色をつけた団子のことである。北信、中信地区で作られるということだが、ぼくは見たことがなかった。涅槃会の派生季語で、地方季語ということになる。
レターパックが厚くなった、「やしようま」を並べ入れると。
ここでは自作した「やしようま」を友人に郵送で届けているのか。厚く、重くなったレターパックの触感を追体験する。「レターパック」という比較的新しい商品と、やしょうまという古くからのものとの出会いが鮮やか。 -
- 名札返す帰寮の友や春の雪
- 山下希記
名札をひっくりかえす、寮に帰って来た友であるなあ、春の雪が降っているよ。
寮の玄関先に寮生全員の名札が掲げられる場所が設けられている。そこを見れば、寮生が寮にいるのか、外出しているのかが、わかるようになっているわけだ。たとえば、表の黒字が在寮、その裏の赤字が外出を意味するようになっているのだろう。春雪の中、帰って来た友が、まず、名札を返して、帰寮を明らかにしたことに、安堵している。「帰寮」ということばも、寮生のことばらしくていい。 -
- つちふるや剝きし卵に小さき傷
- 酒井拓夢
黄砂が降っている、殻を剝いた茹で卵に小さな傷がついている。
剝きし卵で、茹で卵を感じさせているのはうまい。そして、その卵の表面に「小さき傷」を見出したのもありえるところ。たいへん繊細である。「つちふる」と響きあって、内面の傷まで感じさせている。 -
- 天草や朝日映えたる桜鯛
- 松井宏文
天草は、熊本県西部、天草諸島である。桜鯛は、春の産卵時期に腹部が赤みを帯びた鯛である。
天草であるなあ、朝日に映えて桜鯛が上がってくる。
今まさに海の中から釣り上げた鯛に朝日が当たっている状態であろう。
「天草」「朝日」「桜鯛」のa音の頭韻の響き合いもめでたい。 -
- ローンまだ続く墓とふ彼岸道
- 竹村さぎり
ローンがまだ続いている墓である、という、彼岸の道を歩きながら、そんなことを聞いた。
彼岸の墓参に行く道で、その墓のローンが終わっていないことを聞いているわけだ。妙になまなましい事情である。こんな彼岸の句は、初めて見た。
過去のバックナンバーの目次をご覧になりたい場合は、
下記の「澤のバックナンバー」のページよりご覧ください。